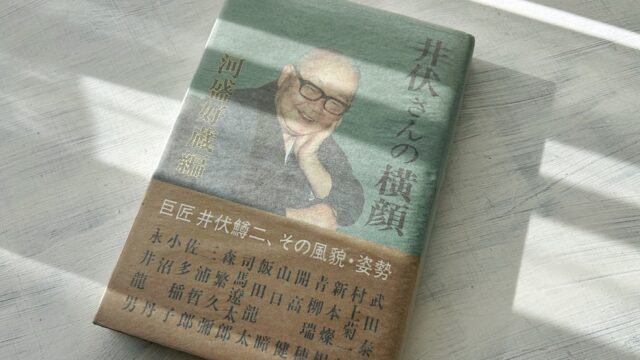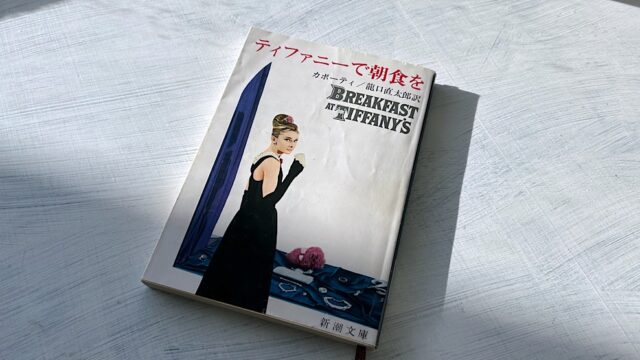小沼丹『木菟燈籠』は、1978年(昭和54年)6月に講談社から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は60歳だった。
収録作品及び初出は次のとおり。
「四十雀」
1978年(昭和53年)1月『群像』
「槿花」
1977年(昭和52年)10月『群像』
「エッグ・カップ」
1977年(昭和52年)9月『文藝』
「鳥打帽」
1977年(昭和52年)8月『海』
「ドビン嬢」
1977年(昭和52年)4月『群像』
「枯葉」
1977年(昭和52年)1月『文藝』
「木菟燈籠」
1976年(昭和51年)10月『群像』
「一番」
1976年(昭和51年)5月『群像』
「入院」
1975年(昭和50年)11月『風景』
「胡桃」
1975年(昭和50年)10月『群像』
「花束」
1971年(昭和46年)10月『群像』
全11篇の短篇小説集
本作『木菟灯籠(みみずくどうろう)』には、全部で11篇の短篇小説が、発表した時期の新しい順に収録されている(後ろへ行くほど古い作品ということになる)。
最も古い「花束」だけは1971年(昭和46年)だが、あとの作品は、1975年(昭和50年)から1978年(昭和53年)までにかけて発表されたもので、1975年(昭和50年)2作、1976年(昭和51年)2作、1977年(昭和52年)5作、1978年(昭和53年)1作となる。
つまり、本書に収録されているのは、ほぼ、1970年代後半(あるいは昭和50年代前半)に発表された作品ということだ。
年齢的には、60歳を目前にした頃の作品が中心ということになる(1978年に60歳となる)。
初出誌としては『群像』が最も多い。
四十雀 │ 林房雄の思い出
1978年(昭和53年)1月『群像』初出の「四十雀」は、鎌倉在住の「林さん」の思い出を綴った作品。
年譜では1949年(昭和24年)5月として「林房雄の勧めで「ガブリエル・デンベイ」(『歴史小説』7月)」とあるから、小沼さんが最初に林房雄に会ったのは、この時期のことだったのかもしれない。
随筆「のんびりした話」(『小さな手袋』所収)にも、「鎌倉の林房雄氏のお宅で御馳走になったことがある」と、林房雄の名前が出てくる。

井伏鱒二を伴って林邸を訪ねたのは、1954年(昭和29年)9月のこと(吉岡達夫も一緒だ
った)。
林さんは、永井龍男を電話で呼び出した後、井伏さんを鎌倉ペン・クラブの例会へと引っ張っていく(久保田万太郎や久生十蘭なども参加していた)。
多分、この后で、酒を飲みながら井伏さんから林さんに就いての昔話を聴いたと思うが、そのとき井伏さんは、林君はいい男なのに誤解ばかりされて気の毒だ、誤解を招く言動もあるが、本当はいい人なんだ、と云う意味のことを云われた。(小沼丹「四十雀」)
井伏さんの言葉には、生きていくことの難しさと寂しさが暗示されている。
林房雄が亡くなったのは、1975年(昭和50年)10月9日で、この作品は、懐かしい人へ送る追悼文のようなものだったのかもしれない。
「みんなみんないなくなった」とあるのは、チャールズ・ラム「古なじみの顔(Old Familiar Faces)」からの引用。
どこへ行ってしまったのだ。あの古なじみの顔は。
遊び友達があった。仲間がいた。
子供の頃の話だ。楽しい学校の日々だった。
みんな、みんな、いなくなった。古なじみの顔が。
チャールズ・ラム「古なじみの顔」福原麟太郎・訳
福原麟太郎の訳は『チャールズ・ラム伝』(1964)で読むことができる。

本作「四十雀」は、林房雄の思い出を軸としつつ、井伏鱒二や吉岡達夫など、脇の登場人物によって、作品としての厚みを増しており、とりわけ重要な存在となっているのが吉田健一だ。
吉田健一は、林房雄の紹介状を持って、鎌倉に住む「白樺」派の小説家の某氏を訪ねてきたところで、「──怕い人かと思っていたら、ちょっと親爺に似ているんで、それで親しみが持てました」と言ったという。
林さんが「──うん、似てますかね……。そう云えばお二人共小柄だし……」と応えているから、これは、志賀直哉ではなく武者小路実篤だったのだろうか。
槿花 │ 松木老人の思い出
1977年(昭和52年)10月『群像』初出の「槿花(きんか)」は、「御承知でもありましょうが……」が口癖だった<松木老人>の物語。
松木老人は、「入院」にも登場している人物だが、この作品の中で亡くなった。
松木老人の死へと、物語を導いているのは、友人と三人で泊まった神戸の宿屋の思い出と、死んだ先妻の兄が経営する医院での検査の話である。
娘(諄子)は医院の敷地内にある別棟に住んでいて、検査の待ち時間は娘の家で過ごす。
ちなみに、「諄子(あつこ)」とあるのは長女の本名で、「大寺さん」に自身を投影した一連の作品とは、やはり、コンセプトが異なっているらしい。
その花を見たら、――槿花一朝の夢……。ひょっこり、そんな文句を想い出した。これが松木の爺さんなら、御承知でもありましょうが、槿花一朝の夢と申しまして、と続く所だがと思う。誰か背後で何か云ったから、「――え?」 振返ったが誰もいない。(小沼丹「槿花」)
「槿花一朝の夢」は、もちろん、我々の一生を象徴するものだっただろう。
木槿が舞台回しとなって、いくつものエピソードを回していく。
エッグ・カップ │ 終戦直後のアメリカ兵
1977年(昭和52年)9月『文藝』初出の「エッグ・カップ」は、終戦直後の銀座で知り合ったアメリカ兵の話。
とりたてて深い交流があったわけではなく、袖振り合うも多生の縁的な物語となっている。
疎開先から戻ってきたばかりの東京が、二人のアメリカ兵に象徴されていたのかもしれない。
大きな兵隊が、「──一緒に少し歩こう」と云うので楽器店を出て、雑踏のなかを一緒に歩いたりしたから、その途中どこかで二人と別れたのだろう。尤も、その前に小さな兵隊は買物をした。(小沼丹「エッグ・カップ」)
年譜には、1945年(昭和20年)10月として「東京に戻る」とあるから、ちょうど、その頃の話だと思われる。
アメリカ兵の思い出の中に「知人の某さんが訪ねて来てロシア旅行の土産話をして呉れた」エピソードが挿入されている。
米兵の一人がアルメニア出身だったことから、アルメニヤ出身の作家ウイリアム・サローヤンにまで話が広がったのだ。
清水俊二・訳『わが名はアラム』は、盟友・庄野潤三の作品にも登場している、サローヤンの代表作だ。

終戦直後の東京が、この物語では描かれているが、決してネガティヴなだけの物語ではないところに、明日への希望が感じられる作品。
鳥打帽 │ 上松さんの思い出
1977年(昭和52年)8月『海』初出の「鳥打帽」は、著者を投影した<大寺さん>を主人公に据えて、大学の同僚<上松さん>の思い出を綴った物語。
学校の制度が新しくなって配属された学部というのは、1948年(昭和23年)に配属された理工学部のこと(この年、著者は31歳だった)。
「大寺さんがその頃或る雑誌に載せた作品を読んだが面白かった」と上松さんが言っているのは、1970年(昭和45年)8月『群像』に発表した「昔の仲間」である(『銀色の鈴』所収)。

上松さんは、何だか昔のことを考えているような顔をした。それから間も無く、上松さんは眼鏡を探しに行くからと立上ったが、その眼鏡が見附かったかどうか、大寺さんは知らない。(小沼丹「鳥打帽」)
冒頭に出てくる「パンの神」(牧羊神)のエピソードも印象的(「矢張り春の一日、高架線の電車に乗っていたら、遠くの屋根の上でパンの神が午睡しているのを見て驚いたことがある」)。
若い時代を共有する先輩教員に向けて書かれた追悼小説である。
ドビン嬢 │ 中村さんの思い出
1977年(昭和52年)4月『群像』初出の「ドビン嬢」は、友人<高田>と、文芸部の先輩<中村さん>の思い出を綴った作品。
萩原朔太郎の「猫町」が『セルパン』に発表された翌年頃とあるから、1936年(昭和11年)くらいだったかもしれない。
喫茶店の女性に対する中村さんの恋心を背景として、二人の人間の人生をぼんやり辿りながら、生きることのはかなさを描き出している。
「ドビン嬢」とは、中村さんが好きだった女性の名前だが(「ドガの画の女に似ていませんか?」)、或る百貨店のドガの展覧会で、主人公は懐かしい絵と再会する。
画の前を離れるとき、画の題を見たら、ちやんと「ドビニ嬢」と書いてあつた。ドビンじやなくてドビニだ、と呟いたら、いや、ドビン嬢だ、高田が怒ってそう云う声がどこかで聞えた。(小沼丹「ドビン嬢」)
友人の高田は、既に病気で亡くなっているし、中村さんの行方も知れない。
絵の前に立ちながら、著者はドビン嬢をめぐる青春の日々を思い出している。
つまり、本作「ドビン嬢」は、あの頃は良かったなあという青春回想記なのだが、古い思い出の話が、全然感傷的でなくてベタベタとしていない。
ドガの作品の前に立って、懐かしいドビン嬢を思い出しながら、「真物を観たら例の娘さんを想ひ出したのはどう云ふ訳か知らない」と、大切な思い出に対してまで、冷たく突き放してみせるのが、小沼丹流の青春回想録なのだ。
ちなみに、読売新聞社主催のドガ展は、1976年(昭和51年)に西武美術館で開催されていたもの。
小沼さんは、このドガ展を観ながら、中村さんや高田のことを思い出したのではないだろうか。
枯葉 │ よっちゃんと植木屋の親爺の思い出
1977年(昭和52年)1月『文藝』初出の「枯葉」は、亡くなった人々の思い出を懐かしく綴った物語作品で、登場人物の一人は、<清水町先生>(井伏鱒二)が懇意にしていた甲府の宿屋の女中<よっちゃん>である。
甲府へ行く前、主人公(小沼丹だろう)は、友人と一緒に、下部温泉に滞在中の清水町先生を訪ねる。
年譜には、1954年(昭和29年)7月として「井伏らと甲府、下部温泉に遊ぶ」とある。
下部では「ここが酒場だ」と書かれた飲み屋の女たちに「あの旅館には『本日休診』と云う、映画にもなった小説を書いた有名な小説家が泊っているそうだが?」と訊かれた井伏さんが「ああ、その人は昨日帰ったそうだよ。俺達は将棋指しだ」と、とぼける場面がある。
下部のあとは甲府にある清水町先生馴染みの宿に泊まるが、深夜、よっちゃんは、清水町先生に「ねんどおたかやん」という歌を教えていて、「――駄目、駄目、先生は音痴かね……」などと、先生を叱っていたという。
或る晩、先生と酒を飲んでいたら、先生がよっちゃんが死んだと云われた。その前后の話も聞いたと思うがよく憶えていない。「──いい人でしたね…」「──うん、よ過ぎたんだ…」一体、あれは何年前になるかしらん?(小沼丹「枯葉」)
知っている人間が亡くなる寂しさは、植木屋の親爺の話でも語られる。
二十何年の交流のあった親爺だから、思い出も尽きない。
秋風というのは、懐かしい人たちを思い出させるらしい。
「そんな秋風に吹かれて歩いていると、遠い昔が甦る気がする。遠い昔が甦って、さらさらと通り過ぎて行く」とあるが、小沼丹の小説は、決して感傷に流されない。
その先の家のブロック塀の上から、何の木か判らないが裸の枝を伸していて、そこに一枚枯葉が残って風に揺れている。その枯葉を見たら、何か想い出すような気がしたが、よく判らないからその儘歩いて行った。(小沼丹「枯葉」)
枯葉は、亡くなった人たちを思い出す懐旧の象徴だが、こうしたタイトルの選び方は、永井龍男の作品でよく見られるものだ。
秋に読みたい短篇小説。
木菟燈籠 │ 小鳥屋・長尾君の思い出
1976年(昭和51年)10月『群像』初出の表題作「木菟燈籠」は、大学の先生(英文科)を辞めて小鳥屋に転職した<長尾君>の物語である。
結局、長尾君は、小鳥屋をあきらめて、学校の先生へ戻るのだが、その経過が、温かみのある視線で描かれている。
春の一日、卓子に頬杖を突いて、ぼんやり庭の梅を見ていたら、垣根の外の路にトラックが停って男の話声がする。ああ、来たな、と思って庭へ出て行くと、裏木戸から長尾君が庭に入って来て、「──石燈籠、持って来ました。どこに据えますか?」と云った。(小沼丹「木菟燈籠」)
長尾君に、学校の先生の仕事を斡旋した<松内君>は造酒屋の息子で、「自分の家の酒は日本一だ」と言う。
そんな挿話が、長尾君の小鳥屋物語に、ちょっとした味付けをしている。
「褐色の根府川石に 白き花はたと落ちたり」とあるのは、森鴎外『沙羅の木』の引用で、主題となっている木菟燈籠との取り合わせもいい。
のんびりした作品だが、運命の巡り合わせの不思議な感じが、よく現れている。
一番 │ 荻窪の寿司屋<ピカ一>の思い出
1976年(昭和51年)5月『群像』初出の「『一番』」は、荻窪にあった鮨屋の物語である。
場所が荻窪だから、<清水町先生>(井伏鱒二)が登場するのは当然で、モデルとなっているのは、荻窪教会通りの「ピカ一」という寿司屋だった。
この物語は、「ピカ一」を回想しながら、井伏鱒二と過ごした懐かしい日々の追憶ともなっている。
寿司屋の主人が将棋好きだったことで思い出した<末さん>の思い出にも、やはり、清水町先生が絡んでいる(「どうかしたんですか?」と清水町先生に訊くと、「何だ、君は知らなかったのか? 死んだんだよ」と言うから驚いた)。
横町の店に行くようになったのは、末さんが死んで十年ばかり経った頃だから、末さんの死んだのは二十年程前と云うことになる。今更驚いても始らないが、いつの間にそんな時間が流れたのかしらん?(小沼丹「『一番』」)
物語のクライマックスは、「一番」のお内儀さんが亡くなったことを知らされたときである。
本作「『一番』」は、鮨屋のお内儀さんを軸としながら、馴染みの飲み屋で出会った人々を懐かしく偲ぶ物語となっていたのだ。
入院 │ 大寺さんの細君の入院
1975年(昭和50年)11月『風景』初出の「入院」は、二番目の細君が緊急入院したときの様子を題材にした短編小説である。
著者(小沼丹)を投影した主人公(大寺さん)が登場する、いわゆる「大寺さんもの」シリーズの作品。
大寺さんの前の細君は夜中に喀血して、血が気管に詰って死んだ。そのときこの医者が車で駆附けて手当したが間に合わなかった。そのときも大寺さんは夜中に電話したことを想い出して、余りいい気持がしなかった。(小沼丹「入院」)
小沼丹の先妻(和子)が急死したのは、1963年(昭和38年)4月のこと。
後妻(純子)と再婚したのは、1966年(昭和41年)12月だから、先妻の死は、主人公(大寺さん)の中に、リアルな記憶を残していただろう。
病院の前で偶然に会った<松木老人>は、「槿花」で主役を担っている人物だ。
「──桜が見事に咲きましたな……」と云って眺めている。大寺さんも一緒になって、陽を浴びた満開の桜を眺めていたら、細君の入院したときは、まだ庭の梅が咲き始めたばかりだったのを想い出した。改めて、あれから一ヶ月近く経ったのかと思う。(小沼丹「入院」)
なかなか咲かなかった梅の花の話が、満開の桜の話で終わる。
これは、<大寺さん>と、その細君の心象風景を投影しているものだ。
梅と桜は、季節の推移を表現すると同時に、<大寺さん>一家の平和な家庭をも象徴していたのかもしれない。
胡桃 │ ブブノワさんの思い出
1975年(昭和50年)10月『群像』初出の「胡桃」は、学生の頃に創刊して二号で潰れてしまった同人誌『胡桃』の話である。
最初『海燕』となるはずだった誌名は、ロアシ人のブブノワさんが描いてくれた表紙絵を、仲間の<金井>が紛失してしまったことで『胡桃』に改められた(「金井」は玉井乾介がモデルで、「昔の仲間」などにも登場)。
「──今度は「胡桃」と云うんです」と云うと、ブブノワさんは、「──おお、胡桃、私の国の木……」と回想的な眼をしたそうである。(小沼丹「胡桃」)
戦争中、信州へ疎開していた主人公は、帰京後に住み始めた小さな家の庭に、胡桃の木を植えるが、風除けのつもりで植えた胡桃は、強風で倒れてしまった。
二個の胡桃を片手で弄んで、カチャカチャ鳴らしていたのは、将棋の好きな<内山さん>である。
内山さんに連れられていった何某さんの家には、アメリカ兵が出入りしていて、何某さんの細君も、アメリカ兵に肩を抱かれていた。
戦争に負けた国の悲哀が、この物語にはある(「――何ですな、戦争に負けるといろいろ思い掛けないことがあるものですな……」)。
現在、使っている胡桃割りの一つは、 チロルのザンクト・アントンで買ってきたもの(チロル旅行の思い出は「ザンクト・アントン」に綴られている。『藁屋根』所収)。

胡桃を舞台回しとして、懐かしい思い出が走馬灯のように語られていく。
花束 │ 毛さん夫妻の思い出
1971年(昭和46年)10月『群像』初出の「花束」は、新宿の酒場でよく見掛けた<毛さん夫妻>の思い出を綴った物語である。
気炎を上げる女子大生や『大菩薩峠』、小鳥屋の九官鳥、「アムステルダムの水夫」、おかめ鸚鵡など、脇の小道具が良い味を出している。
ほのぼのとした話だが、しばらく見掛けなかった毛さんが、実は鉄道自殺していたという結末は寂しい。
いつだったか毛さんの奥さんが大きな花束を抱えていたのを想い出した。あれは何の花束だったのだろう? 毛さんも奥さんもにこにこしていて愉しそうだったから、そのときは何かいいことがあったのだろうと思ったが、或はそれは思違だったのかもしれない。そう思ったら不意に空気が動かなくなって、辺りがしいんとしたような気がした。(小沼丹「花束」)
題名の「花束」は、毛さんの奥さんが抱えていた、大きな菊の花束のこと。
「何か良いことがあったのだろう」と、主人公は受け取ったが、他人の運命なんて分からないという、人生のはかなさが伝わってくる。
まとめ │ みんなみんないなくなった
小沼さんの小説は、感傷に流されそうで、実は流されないというところに、一つの黄金パターンがある。
「誰か背後で何か云ったから、――え? 振返ったが誰もいない」「真物を観たら例の娘さんを想い出したのはどう云う訳か知らない」「何か想い出すような気がしたが、よく判らないからその儘歩いて行った」など、感傷に惹かれた読者を突き放すような展開は、小沼文学では珍しくないだろう。
小沼さんの小説は、そもそもがセンチメンタルな思い出で構成されているので、必要以上に感情に流されては、文学が湿っぽくなっていけない。
そのような作者の思惑が、作者自身(のペン)にブレーキをかけているのかもしれない。
「四十雀」でも引用されているチャールズ・ラム「古なじみの顔(Old Familiar Faces)」は、小沼文学を通底する主旋律だ。
「みんなみんないなくなった」という詩情こそが、小沼丹の小説の原動力となっているのだろう。
いずれ、自分も含めて「みんなみんないなくなってしまう」からこそ人生は素晴らしいという、生きることへの畏怖が、そこにはある。
そして、そのことを誰よりも知っていたのが、度々登場しては登場人物の死を告げる<清水町先生>こと、井伏鱒二だったのかもしれない。
書名:木菟燈籠
著者:小沼丹
発行:2016/12/9
出版社:講談社文芸文庫