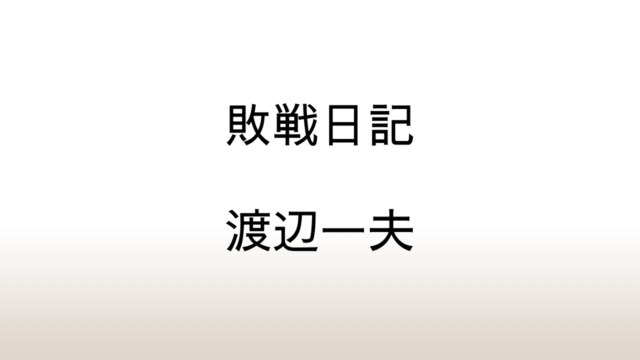奥野信太郎「町恋いの記」読了。
この中国文学者の書いた随筆集には、おもしろいものがたくさん入っている。
自立した大人の粋な生き方を学ぶ
冒頭「六本木界隈」は、昭和40年前後の六本木の様子を描いたもので、赤坂の山王境内に移った「鰻の大和田」は山の茶屋として営業しており、文壇句会はいつもここに席が決っているが、久保田万太郎が亡くなってからは歯の抜けたような寂しさである。
「未完成はつねに美しい」では、毎日歩く渋谷の街をテーマとしており、「渋谷のよさは、町全体がまだまだ未完成だという点にある」と、発展途上にある渋谷の街の将来への期待を寄せている。
楽しいのは「私の健康法」で、「少なくともぼくの健康にはたいへんに力になっていることだと思っていること」として、著者は「世のなかの制約というか、拘束というか、そういうものを守らないことである」と綴っている。
それはどういうことかというと、出席で伝えておいた夜の会合があっても、気分次第では直前にキャンセルをしてしまうというもので、しがらみの多い世の中で、この自由な生き方は、まさしくうらやましいものだ。
宴会をドタキャンした著者は、古本屋を梯子した後で遠くの居酒屋で一杯やっているわけで、「この気随気ままが実はぼくにとっては、かけがえのない安心立命の源となっているのだ」とあるのもうらやましい。
自立した大人の粋な生き方として記憶しておきたい。
「おしゃれ上手」はファッションに触れた作品で、「わたくしはおしゃれをしていますというおしゃれは、どうしても好きになれない」「あのひとは、ごく無造作に、一見少しもしゃれ気のないように見えるけれども、どうしてなかなかおしゃれだという、そういうおしゃれに、一番心をうたれる」というファッション観は、管理人としても日頃強く意識していることであり、この古い随筆に強く共感を抱いてしまった。
文士劇のとき、”おそめ”のママの上羽秀さんから差し入れのあった京都”いづう”のちらし鮨は、立派な漆器に入っていたが、文士劇の参加者はプラスチックの容器だと思って捨ててしまった。
河盛好藏が、後になって貴重なものを捨ててしまったと嘆いたという話は、「心づくし」という作品の中に出てくる。
文学的随筆に対する強い関心
丸岡明の細君である山川美耶子さんは、石井柏亭、有島生馬、山下新太郎の書画伯に愛された美女で、結婚して以来、年を取るほどに美しくなっていった。
一方の丸岡明は年齢よりも老けて見えるので、二人が並んでいると、まるで親子のようであると「親父が娘を」に書かれている。
この美耶子さんは料理も上手で、死んだ十返肇は「われわれのところではお惣菜を食べているが、丸岡のところでは毎日料理を食べている」と感心していたそうである。
後半には書評や文学批評も入っていて、里見弴「極楽とんぼ」、久保田万太郎「むかしの仲間」、谷崎潤一郎「三つの場合」などが紹介されている。
中でも、谷崎潤一郎の「三つの場合」は、「随筆にはおのずから二種類あって、四季おりおりの風物に発した純粋の感想を、さりげなく述べたものと、またそれとは別に、やや小説的な構成をもって筆を進めてゆくものとがある」「谷崎潤一郎氏の近著「三つの場合」は、その両面をみせた随筆として異色のものであり、なかなか読みごたえのあるものであった」と高い関心を示している。
ちなみに、「三つの場合」には表題作のほか十篇の短い随筆が収録されているが、著者は「吉井勇翁枕花」と「親父の話」に最も興味を惹かれたらしい。
随筆集としては、佐藤春夫「白雲去来」「続白雲去来」も紹介されていて、「ちかごろは随筆と銘をうって、その大部分が非文学であることを、ぼくははなはだ痛憤している」「いわゆる座興に読むもののなかにも、十分エスプリを感じ得られるものもないではないが、そういうものに出あうことはまずまれである」「もっとも本格的な文学的随筆として、佐藤春夫氏の「白雲去来」および「続白雲去来」を一読して、日ごろの欝憤が消しとぶ思いがした」と、随筆に対する強いこだわりを隠していない。
随筆への思いは「著者は、文学作品のなかにおいて随筆というものを重くみて書いている。この点、その日比を求めるならば永井荷風以外にはこれをみないであろう」という文章からも、十分に伝わってくる。
随筆に対して強いこだわりを持つ著者だからこその文学的なエスプリが、本書には十分に備わっているということが言えそうだ。
書名:町恋いの記
著者:奥野信太郎
発行:1967/8/25
出版社:三月書房