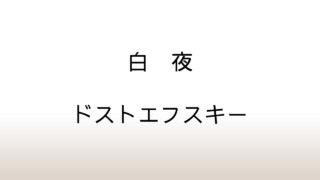庄野潤三「野鴨」読了。
本作『野鴨』は、1973年(昭和48年)1月に講談社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は52歳だった。
初出は、1972年(昭和47年)1月~10月『群像』。
『明夫と良二』に続く家族の物語
昭和40年代、庄野さんは、「和子・明夫・良二」という三人の子どもたちが活躍する五人家族の物語を書き続けた。
そのほとんどは短編小説で、「丘の明り」「星空と三人の兄弟」「戸外の祈り」「小えびの群れ」「さまよい歩く二人」などの作品を積み重ねた末に、1970年(昭和45年)、第24回野間文芸賞を受賞する「絵合せ」を発表。

さらに、1972年(昭和47年)4月には、明夫と良二シリーズの集大成とも言える書き下ろしの長篇小説『明夫と良二』を刊行し、第2回赤い鳥文学賞と第26回毎日出版文化賞を受賞するが、ここが、五人家族の物語の一つの到達点となった。

五人家族の中軸だったとも言える長女・和子が結婚をして「山の上の家」を出て行ったことで、「五人家族の物語」は、二度と書くことができなくなってしまったのだ。
本作『野鴨』は、『明夫と良二』が出版されたときに『群像』で連載中だった長篇小説で、時系列的には、『明夫と良二』以降の井村家の様子が描かれている。
ただし、以前のような子どもたちを中心とした物語から、より幅広い視点をもった家族小説へと発展していることが、本作『野鴨』の大きな特徴と言えるだろう(同時期の作品ながら、味わいはかなり異なる)。
次男の良二でさえ高校二年生だから、いつまでも少年の役を務めているわけにはいかない。
それでも、明夫と良二の兄弟は、この長篇小説でも活躍していて楽しい。
例えば、夕食のゆで卵を争奪する二人の姿。
「明ちゃん、やめて」良二は、哀れな声を出した。「やめなさい、明夫」妻が叱った。(庄野潤三「野鴨」)
食事時にもめ事が起きるのは、この家族にとって、文字どおり日常茶飯事で、「明ちゃん、やめて」は、口癖とも言える良二の悲痛な叫びである。
家を出た長女(和子)は、すぐ近所に住んでいるので、作品にはたびたび登場する。
今度も妻と二人で来るつもりでいた。ところが、前の日の午後に駅の方まで行った妻が、道で子供をおぶった和子に出会った。和子はもう用事が済んだあとなので、つき合いますというから、一緒に坂道を上って市場へ寄り、ついでに家まで来た。(庄野潤三「野鴨」)
『明夫と良二』で結婚した和子に、もう最初の赤ん坊が生まれている。
このとき、井村夫人が「だるま市へ行く」という話をすると、和子も、子どもを連れて一緒に行くことになった。
前の年に井村夫妻は、夫婦でだるま市へ行った。
その前の年は、高校生だった明夫に、だるまを買ってきてもらった。
だから、井村夫妻がだるま市を訪ねるのは、昨年に続いて二回目で、和子にとっては初めてということになる。
前の年、だるま市の帰りに井村夫妻は、中華そば屋で湯麺(タンメン)を食べた。
前の年は、井村は妻と二人で来た。帰りに、駅の近くの中華そばの店へ入って、湯麵を食べた。赤ん坊のいる夫婦でしている店で、そこの湯麺がキャベツももやしもたっぷり入っていて、汁は丼のふちにすれすれになるくらいで、味がよかった。(庄野潤三「野鴨」)
「これからだるま市の帰りはここへ寄って昼食ということにしよう」と夫婦は約束するが、柿生のだるま市と生田駅前「味良(みよし)」のタンメンは、「夫婦の晩年シリーズ」に至るまで、長く庄野夫妻の年中行事となった。

『野鴨』では、大阪で暮らす井村の家族のことも綴られている(井村夫婦は、もともと大阪の出身だった)。
井村夫婦が、幼稚園へ行っている女の子と二つになる男の子を連れて、東京へ引越してから、もう十八年になる。十年ひと昔というが、ひと昔の上に、まだもう昔、積み重ねようとしている。(庄野潤三「野鴨」)
校長をしていた井村の父は戦後に亡くなり、井村の長兄も、父より二年先に急死してしまった。
井村の上の兄は、中学のころから水泳の選手で、専門の水泳ばかりでなく、運動競技というものが本当に好きであった。性質は真面目で、責任感が強く、几帳面であった。(庄野潤三「野鴨」)
本作『野鴨』では、亡くなった長兄に関するエピソードが、随所に登場する。
この長篇小説が、長兄の長女(井村の姪)の結婚式の案内状から始まっているのも、この物語と死んだ長兄との関わりが深いことを暗示している。
兄の夢を見るエピソードは、その象徴的なものとも言えるだろう。
「兄の夢は久しぶりだったな」もう一週間くらいになるだろうか。お彼岸になる前であった。朝がた、亡くなった長兄に会って、何かひとこと、ふたこと話す夢を見た。(庄野潤三「野鴨」)
病気で入院しているときの長兄が描かれる作品は珍しい。
亡くなった長兄のところに民子が生れたのが、戦争の終った翌年であり、次の年に井村のところに和子が、その次の年に二番目の兄のところに昌子、長兄のところに智子が生れた。続けてどこの家にも女の子が生れた。(庄野潤三「野鴨」)
生田の「山の上の家の物語」だった家族小説が、『野鴨』では、壮大な井村一族の物語としての性質を見せている。
長兄の次女(智子)は、神戸を舞台とする『早春』(1982)に「智ちゃん」として登場している(神戸で結婚式を挙げた)。

ここに描かれている子どもたちは、みな「団塊の世代」と呼ばれる子どもたちだ。
「お母さんとお義姉さんを誘って、みんなでてっちりを食べに行ったことがありましたね」(略)「お隣りとうちの家族で行ったの。民子ちゃんも智子ちゃんも一緒に」(庄野潤三「野鴨」)
母親をてっちりへ連れて行った記憶は、井村にとって、唯一の母親孝行の記憶として残っている。
フグ鍋の終わりに、井村家の人々は雑炊を食べた。
おいしいから、いくらでも食べたいが、おなかが一杯になって、もうこれ以上食べられない、残念だというので、この雑炊を「残念雑炊」というんですと、板場さんが話した。「あれが、ざんねんのはじまりか」(庄野潤三「野鴨」)
以来、井村の家では、豚肉の水炊きの後に食べる雑炊を「ざんねん」と呼ぶようになった(正確には雑炊ではなくて、ご飯に鍋のスープをかけたものだが)。
家族という糸が、東京から大阪へと繋がりながら(横糸)、現在から過去へとも繋がっている(縦糸)。
本作『野鴨』は、横糸と縦糸を巧みに操って、立体的な家族小説を構築しているのだ。
そして、子どもの(小学4年生だった和子の)作文を通して語られる懐かしい日々。
今日はお父さんがこんな話をしてくれました。お母さんが、お使いに行って、お父さんがひとりだけの時のことです。赤ちゃんがねむくなって、目をこすり出したので、お父さんが、「ねんね」というと、くずれ落ちるようにふとんに顔をふせました。(庄野潤三「野鴨」)
「赤ちゃん」というのは、次男(良二)のことだが、和子のところに生まれた赤ん坊の話を通して、井村は、子どもたちが幼かった日のことを思い出している。
「ボールけり」という作文もいい。
和子の作文に出て来る家族は、家の中でまりの蹴り合いなんかしているが、収入は全く少なかった。一度、玄関の呼鈴が鳴って、井村が出てみると、押売りでもなく、浮浪者でもない風態の男が立っていた。(庄野潤三「野鴨」)
「金、下さい」と言った男に、井村は「金、ないの」と答える。
剃刀まけが治らない井村は、髭を伸ばしたきりの顔で「金、ないの」と、手を振った。
この「金、ないの」という言葉が、家族の中で流行したという思い出話である。
その頃、庄野さんは、作家として独立するための苦労を重ねている時期だった。
もうそのころは、井村は勤めていた放送会社をやめていた。やめて一年たっていた。物を書いて暮しを立てるということが、どんなに容易でないか、少しずつ分りかけて来た時分であった。(庄野潤三「野鴨」)
大阪での暮らしも、サラリーマンを退職した日々のことも、小説家としての庄野潤三にとっては、原点と言えるものだっただろう。
原点回帰という意図が、この作品からは伺うことができる。
お父さんが二かいから「ああ、ピンチだ」といっておりて来ました。お母さんが「なにがピンチなの」というと、お父さんは「げんこうを五まい書いて、またはじめから書きなおしだ」といったので、私が「五たい〇と、五まい書いてはじめから書きなおすのと、だいたいおなじことね」といったので、家じゅう大わらいをしました。(庄野潤三「野鴨」)
作家として必死に生きている井村(つまり、庄野さん)の姿が、そこにはある。
生きていることは、やっぱり懐しいことだな!
本作『野鴨』では、家族小説に膨らみを与える上で、文学作品が、大きな効果をもたらしている。
例えば、庭の野鳥のために与えたパン屑を見て、グリム童話を思い出す話。
良二の寝台のうしろに本棚がある。グリム童話集は、よく借り出すので、大体どの辺にあるかということは吞み込んでいる。彼は、子供の寝台に腰を下して、「ヘンゼルとグレーテル」のところを開いてみた。(庄野潤三「野鴨」)
「ヘンゼルとグレーテル」を読みながら、井村は、学生の頃に読んだ「赤い胸の駒鳥の話」を思い出す(残念ながらタイトル不明)。
庭の野鳥から「ヘンゼルとグレーテル」へと広がった話は、「赤い胸の駒鳥の話」へと脱線していき、「ヘンゼルとグレーテル」を経て、再び、庭の野鳥へと戻ってくる。
こうした文学的寄り道は、庄野文学の得意とするところで、物語の筋(ストーリー)よりも、語りの展開を楽しむところに、庄野潤三という作家の魅力がある。
こうした文学の話は、ぼんやりと庭を眺めているときに生み出されることが多い。
手を伸ばせば届くところに、本棚の隅の方に、一冊の名言集がある。英米編という中にいいのがいっぱい詰まっている。航海士は、「船が沈みかかっています」という。(略)すると、船長は答える。「船ってものは、進水した時から、沈みかかっていたと思っていいんだよ」(庄野潤三「野鴨」)
いかにも庄野さん好みの、この話の出典は、福原麟太郎の『永遠に生きる言葉』だった。
さらに、井村は『英語歳時記』の「春」を取り出してきて「あふれる溝」という言葉を調べる。
「あふれる溝、雪どけごろ」それは最初の方に出て来る。その前に「四月」「四月の日」「四月のたそがれ」というのがある。アルファベット順だからそうなる。それから「早春」が来る。(庄野潤三「野鴨」)
庄野文学では、「随筆みたいな小説」という表現が多用されるが、殊に『野鴨』では、随筆的な味わいが濃い。
これは、福原麟太郎が愛読した『エリア随筆』(チャールズ・ラム)に代表されるイギリス・エッセイ文学への挑戦を試みたものではなかっただろうか(連載小説という体裁を取ってはいるが)。

そのチャールズ・ラムは、作家名を特定されない形で、さりげなく登場している。
昔、ロンドンの街を、夜明けとともに現れる少年の煙突掃除人が、声を張りあげて通った。その声は、若い雀のように可愛らしかったといわれる。井村は、学校にいる時分に、英語の本の中で出会った文章の、始まりのところを思い出した。(庄野潤三「野鴨」)
庭の野鳥の中に、古いイギリスのエッセイが、さりげなく溶け込んでいる。
書名は出てこないが、桜庭信之の『絵画と文学 ホガース論考』も、当時の庄野さんが愛読した書籍のひとつだ。
十八世紀のころのロンドンでは、朝早く、まだ子供が目を覚まして起きて来ないうちに、しぼり立ての牛乳の入った桶を頭にかついだ娘さんが、通りを歩きながら、大きな声で呼んだらしい。これも耳学問で、英国の一人の画家について書かれた評伝の中に出て来る。(庄野潤三「野鴨」)
ちょうど、その頃、井村の友人が、ロンドンで暮らしていた。
井村の友人は、ロンドンの西部にある古い住宅町に借家を見つけて、少し前に勤めをやめた下のお嬢さんと二人で暮しているのだが、ウエンブレイは彼のいるところから地下鉄で三つ四つ先の郊外の駅で近い。「娘と一遍みに行こうかと話していたところでした」(庄野潤三「野鴨」)
「黍坂にいる和子が小学一年のころからのつき合い」とある、この友人は、作家の小沼丹で、小沼丹の英国滞在は、後に『椋鳥日記』(1974)という名作に綴られることになる。

友人からの手紙を通して、井村は、昔イギリスに滞在したことのある父親のことを思い出す。
井村は、昔、ロンドンで市内の学校を参観してまわっていた父のことを思い出した。それは、彼が小学一年のころだから、随分昔になる。父が下宿していたのは、ロンドンのどの辺だろう。(庄野潤三「野鴨」)
日常の中に、古い記憶が、さりげなく這入り込んでくる。
というより、庄野文学において古い記憶は、現在の日常と切り離すことのできないものだ。
現在の日常は、古い記憶の積み重ねによって作られていると言ってもいい。
日常生活のひとつひとつに、井村が経験した物事の記憶が、分離できないくらいに溶け込んでいるのだろう。
「生きていることは、やっぱり懐しいことだな!」という言葉に表される庄野哲学が、そこにはある。
何気ない暮らしの中にも歴史の蓄積があるから、庄野潤三の作品は奥が深い。
壮大な空想物語を展開する以上の深さが、庄野文学の家族小説にはあるのだ(考えてみると、それは当たり前のことなのだが)。
むしろ、歴史を積み重ねてきた家族以上に、壮大な物語はないとも言える。
ささやかな日常生活こそが、壮大な物語を感じさせることができるというパラドックス。
『野鴨』は、ある意味で、実験的な作品だったのではないだろうか。
「さて、早いもので」庭を眺めたままで、もう一度、呟いてみる。どうしてこのひとことがいいのか。或いは型通りであるかも知れないこの言葉が、井村の胸にしみじみと納まるのはなぜだろう。(庄野潤三「野鴨」)
長兄の姪の結婚式の案内状から始まった物語は、両親と長兄の法事の案内状で終わる。
「さて、早いもので」という挨拶状の文句は、冒頭「もう一ヵ月になるんだな」と呟いた井村の言葉に対応している。
家族小説という循環の物語。
生きることの懐かしさを、我々は、この小説でも楽しむことができるのだ。
本作『野鴨』は、読み込むほどに味わいが出てくる、奥の深い家族小説である。
ハラハラドキドキする場面はないかもしれない。
しかし、生きていることの懐かしさを、しみじみと嚙みしめることはできる。
大人になると、どうして、このような小説が愛しくなるのだろう。
それは、我々自身こそが、懐かしさの中に生きていることの証明に他ならない。
すべての人は、古い記憶の積み重ねの中に生きているのだ。
書名:野鴨
著者:庄野潤三
発行:1973/01/16
出版社:講談社