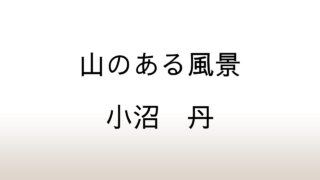村上春樹「やがて哀しき外国語」読了。
本作「やがて哀しき外国語」は、1992年(平成4年)8月から1993年(平成5年)11月まで『本』に連載されたエッセイである。
連載開始の年、著者は43歳だった。
単行本は、1994年(平成6年)2月に講談社から刊行されている。
プリンストンのスノッブな大学村生活
本作『やがて哀しき外国語』は、村上春樹がアメリカのプリンストン大学に客員教授として招聘されていた時期に、日本の雑誌『本』に連載された作品を書籍化したものである。
プリンストン大学は、村上春樹の好きなF・スコット・フィッツジェラルドの母校で、ここで村上春樹は、かなりスノッブな大学村生活を過ごしていたらしい。
アメリカにいて日本のことを考えているから、日米比較文化論みたいなエッセイ集だけれど、別にそんな難しいことを論じているわけではない。
アメリカのマラソン大会と日本のマラソン大会の違いについて論じたりとか、そういう生活レベルにおける日米文化の比較が、村上春樹的世界観によって行われているだけだ。
例えば、マラソン大会の出場者名簿を作成・配布するというのは、アメリカにはない文化らしい。
僕はこの名簿を見るたびにいつもなんとはなしに複雑な気持ちになってしまう。そして「ああ、俺は結局この世界のどこにも何にも属していないんだなあ」とあらためて実感することになる。正直に言って、そんなことをよく晴れた気持ちの良い日曜日の朝からいちいち実感させてほしくないと思う。(村上春樹「アメリカで走ること、日本で走ること」)
こういう文章を読んでいると、そうそう、村上春樹って、こういうエッセイを書いていたんだよなあということを、改めて実感することができる。
枚数に余裕があったせいか、割と、どうでもいいことを、くどくどと長く綴っているのが、このエッセイ集の特徴といえばいえるだろうか。
日本では何かがあると「村上さんはベストセラーを書いてお金持ちなんだから、これくらいのことは」と言われる。そりゃそうかもしれないけれど、はっきり言って余計なお世話である。(村上春樹「大学村スノビズムの興亡」)
こういう文章も、村上春樹らしくていい。
村上春樹らしい表現ということでは「文化的焼き畑農業」というのもある。
でも日本ではそう簡単にはいかない。たとえばオペラなんて流行じゃないよ、今はもう歌舞伎だよ、という風にどうしてもなってしまう。情報が咀嚼に先行し、感覚が認識に先行し、批評が創造に先行している。それが悪いとは言わないけれど、正直言って疲れる。(村上春樹「大学村スノビズムの興亡」)
その点、スノッブな大学村では、コレクトとインコレクトがはっきりしているから、時代や流行に流される必要がない。
とにかく『NYタイムズ』を読んでおけばいい、とにかく『ニューヨーカー』を取っておけばいい、とにかくオペラを聴いておけばいい、とにかくガルシア・マルケスとイシグロとエイミー・タンを読んでおけばいい、とにかくギネス・ビールを飲んでおけばいい、といったルールがはっきりしている。
考えようによっては、「神経症的な」日本の「先端的波乗り競争」に加わるよりも、ずっと健康的な生き方なのかもしれない。
「焼かれずに生き残る」ことを念頭において、「傍目によく映る」ことだけを考えて活動しなければならない日本で文化的な活動をするというのも、実は、なかなか大変なことなのだ(これを「文化的消耗」という)。
村上さんのアメリカでの生活を知ることができるのは「誰がジャズを殺したか」。
アメリカに来て暮らすようになってから、中古レコード店をまわってジャズの古いレコードを漁ることが、大きな楽しみになってしまった。いちばんの娯楽と言ってもいいくらいだ。せっかく外国に住んでいるのだから、もう少し有意義で活動的な人生の楽しみかたがあってもいいのにと、ときどき自分でも思うのだけれど。(村上春樹「誰がジャズを殺したか」)
1990年代初頭というと、レコードからCDへの移行がほぼ完了して、レコードの将来性なんか、ほとんどないと思われていた時代ではなかっただろうか。
CDに切り替えたユーザーからの放出で、在庫も豊富だっただろうし、この時期に中古レコード店巡りをできたということは、きっと幸せなことだったんだろうなと思う。
この時期に村上さんが読んでいた本が、伝記や自叙伝だ。
しかし外国人によって書かれた伝記や自叙伝というのはどうしてこう面白いんでしょうかね? 読みだしたら止まらない小説というのは最近アメリカでも稀だけれど、読みだしたら止まらない伝記というのはけっこう数多くある。そんなわけで、ここのところ小説はひとまずおいて音楽家の伝記のようなものを何冊かまとめて読んでいた。(村上春樹「バークレーからの帰り道」)
こういう文章を読むと、すぐに影響を受けて、外国の伝記を読みたくなってしまう。
最近、読書のテーマ性に乏しいので、どこかで「伝記・自叙伝」月間とか、やってみようかな。
レイモンド・チャンドラーとかトルーマン・カポーティとかケストナーとか、まだ読んでいない作家の伝記本が、本棚で順番待ちをしているし。
厚い本って、どうしても躊躇しちゃうんだよね。
普通のサラリーマンにとって、読書に充当することのできる時間っていうのは、案外と限られているものなので。
おもしろいのは、「奥さんは何をしているのか」と訊かれたとき、アメリカでは返答に窮するという話だ。
一般に、アメリカで専業主婦というのは許されないみたいで、小説家である夫の補助をしているという答えも、アメリカでは納得を得られないものらしい。
しょうがないので、そこまで言われると僕も奥の手を出してきて、「実は彼女は写真をやっているんです」と言うことにしている。ヨーロッパに住んでいるときにはうちの奥さんは、僕が旅行記を書くための記録カメラマンのような役をしていたのだけれど、後日それに目をとめてくれた人がいて、小さな写真集のようなものを出したことがある。そのことを持ち出すのだ。(村上春樹「元気な女の人たちについての考察」)
村上陽子さんの写真集『風のなりゆき』は、1991年(平成3年)にリブロポートから刊行されているが、現在では入手困難。

村上さんの奥さんの撮った写真を見たかったら、村上さんの『うずまき猫のみつけかた』を読むしかないだろう。
この「元気な女の人たちについての考察」では、村上春樹と陽子夫人とのなれそめが綴られているので、興味のある人にはお勧めです。
これから小説家になりたいと考えている若い人たちのために
割と、どうでもいい話題が多い中で、「ロールキャベツを遠く離れて」は、意外とまともな話である。
ロールキャベツというのは、村上春樹が作家になる前、飲食店を経営していた頃の象徴的なキーワードだ(これも村上春樹らしい)。
ひとつ例をあげると、僕の店はロールキャベツを出していたので、朝から袋いっぱいの玉葱をみじん切りにしなくてはならなかった。だから僕は今でも、大量の玉葱を短時間に、涙も流さずにさっさっさと切ることができる。本当に手が自然にさっさっさと動いてしまうのだ。(村上春樹「ロールキャベツを遠く離れて」)
これは、これから小説家になりたいと考えている若い人たちのために書かれた文章なので、いつか、村上春樹みたいな小説家になりたいと考えている人は、読んでおいて損はないと思う。
はっきり言って、本書『やがて哀しき外国語』の中で、必ず読んでおくべきエッセイの一つである。
というか、このエッセイを読むためだけに、この本を買うのもありだと、僕は思っている。
僕自身だって、二十歳の頃はやはり不安だった。いや、不安なんていうようなものじゃなかった。今ここに神様が出てきて、もう一度お前を二十歳に戻してあげようと言ったら、たぶん僕は「ありがとうございます。でも、べつに今のままでいいです」と言って断ると思う。こう言っちゃなんだけど、あんなもの一度で沢山だ。(村上春樹「ロールキャベツを遠く離れて」)
二十歳の頃の話なんて、なんとなく村上春樹の短篇小説「バースデイ・ガール」を連想させるエピソードかもしれない。
おすすめ。
そして、もうひとつ、このブログに関わるエッセイとして「さらばプリンストン」がある。
これは、プリンストン大学のセミナーで、日本の「第三の新人」をテーマに、大学生とディスカッションしたときの話で、もちろん、後の『若い読者のための短編小説案内』に繋がるエッセイだ。
庄野潤三の『プールサイド小景』『静物』や小島信夫の『アメリカン・スクール』は、学生時代に読んで深く印象に残った、僕にとっては数少ない日本の小説のひとつである。第一次、第二次戦後派なんかに比べると、「私小説的」と評されることの多いこの人たちの小説群に、なぜ僕が(申し訳ないけど「私小説」アレルギーのこの僕が)このように心引かれるのかというのが、このセミナーにおける僕自身の個人的なテーマだった。(村上春樹「さらばプリンストン」)
このブログサイトでは、村上春樹と庄野潤三の二人を、大きなテーマに位置付けているのだけれど、村上春樹と庄野潤三という対照的な二人の作家の作品を、同時に愛読しているということは、僕自身にとっても、実は大きな謎の一つだった。
村上春樹のエッセイを読むと、そこにはやはり、何かしらの共通点というか、類似点のようなものが、きっとあるのだという気がしてくる。
その「何か」は、今のところまだ不明で、その理由を見つけるまで、僕の読書ブログの旅は続くのかもしれない。
ちなみに、学生たちがペーパーで取り上げたテキストの中で一番多かったのは、庄野潤三の『静物』だったということである(次が、安岡章太郎の『悪い仲間』『海辺の光景』)。
僕は、頭休めをしたくなったときには、村上春樹のエッセイ集を読むことにしている。
凝り固まった頭の中をリセットする上で、村上春樹のエッセイが有効に機能しているような気がするからだ。
特別に難しいことでもないんだけれど、書き捨てのコラムとも違うので、文章をしっかりと読んでいるという充足感も得られる。
何より、F・スコット・フィッツジェラルドとか、ブルックス・ブラザーズとか、スティーヴン・キングとか、レイモンド・カーヴァーとか、マイルス・デイヴィスとか、ポール・オースターとか、そこで語られている世界観に共鳴できるんだろうなあ。
僕は、村上春樹の小説以上に、村上春樹のエッセイが好きです、はっきり言って。
書名:やがて哀しき外国語
著者:村上春樹
発行:1997/02/15
出版社:講談社文庫